トランプ関税とは?第1期の影響と第2期(2025年現在)の日本への影響を解説
「トランプ関税」という言葉を連日ニュースなどで聞くことが増えたと思います。ドナルド・トランプ氏が2025年1月に再び米国大統領に就任し、その政策、特に貿易に関する方針に世界中の注目が集まっています。「トランプ関税」でいったいなにがおきるのか?
かつて日本にどのような影響があったのか? そして、これから日本や世界経済、投資の世界にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか?
この記事では、「トランプ関税」の基本的な意味から、第1期トランプ政権下での具体的な措置とその影響、そして現在(2025年4月時点)の第2期政権下で懸念される日本への影響や今後の展望について、わかりやすく解説していきます。「トランプ関税」とは何かを理解し、今後の経済や市場の動きを見通すための参考にしてください。
トランプ関税とは?用語を徹底解説
トランプ関税の基本的な意味と目的
「トランプ関税」とは
ドナルド・トランプ米大統領の政権下で導入が検討・示唆されている一連の追加関税措置の総称
です。これは特定の法律名や協定名ではなく、トランプ氏の「アメリカ・ファースト(米国第一主義)」に基づいた保護主義的な通商政策を象徴する言葉として使われています。
つまり、いいかえれば
トランプ大統領が行おうとしている関税政策(による関税)
を指します。
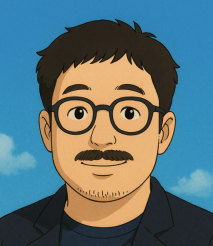
実際に「トランプ関税」という種類の関税があるわけではありません
まずは第一期で行われたトランプ関税について振り返りましょう。
第1期政権下で掲げられた主な目的は以下の通りです。
- 米国の貿易赤字削減: 特に中国など、米国が巨額の貿易赤字を抱える国々との貿易不均衡を是正することを強く主張しました。関税によって輸入品の価格を上げ、輸入を抑制し、国内生産品への代替を促す狙いがありました。
- 国内産業の保護: 鉄鋼、アルミニウム、自動車といった、外国製品との競争によって衰退したとされる米国内の基幹産業を保護し、競争力を回復させることを目指しました。
- 国内雇用の確保・回復: 製造業など、国内産業の活性化を通じて、米国内の雇用を取り戻し、労働者の支持を得ることも重要な目的でした。
- 国家安全保障の確保: 特定の輸入品(特に鉄鋼やアルミニウム)の輸入増加が、米国の安全保障上の脅威になるとして、米通商拡大法232条という法律を根拠に関税を課しました。これは従来の通商政策ではあまり用いられなかった手法です。
- 他国との交渉手段: 関税を「武器」のように用い、他国に対してより有利な貿易条件や譲歩を引き出すための交渉カードとして利用する側面も強く見られました。
これらの目的のもと、第1期政権では様々な関税措置が打ち出されました。
第1期トランプ政権下の主な関税措置(振り返り)
トランプ前政権(第1期)が実施した、あるいは実施を示唆した主な関税措置を振り返ってみましょう。これらが「トランプ関税」の具体的な中身となります。
鉄鋼・アルミニウム関税(通商拡大法232条に基づく措置)
2018年3月に発動され、安全保障上の脅威を理由に、多くの国(日本、EU、カナダ、メキシコなど同盟国含む)からの鉄鋼輸入品に25%、アルミニウム輸入品に10%の追加関税が課されました。各国からの反発を招き、一部の国とは関税の代わりに輸入数量制限を設けるなどの合意に至りましたが、日本に対しては関税が維持されました(その後、バイデン政権下で一部見直し)。
対中関税(通商法301条に基づく措置)
中国による知的財産権の侵害や技術移転の強要といった不公正な貿易慣行に対抗するとして、2018年7月から段階的に、合計で数千億ドル規模の中国製品に対して最大25%の追加関税を課しました。対象品目はハイテク製品から日用品まで多岐にわたりました。中国も米国からの輸入品(大豆、自動車など)に報復関税を発動し、「米中貿易戦争」と呼ばれる激しい貿易摩擦に発展しました。2020年1月に「第一段階の合意」がなされましたが、多くの関税は維持されたままでした。
洗濯機・太陽光パネルへのセーフガード
2018年1月、韓国などからの洗濯機や太陽光パネルの輸入急増が国内産業に損害を与えているとして、緊急輸入制限(セーフガード)措置を発動し、追加関税を課しました。
自動車・自動車部品への関税検討(232条)
日本やEUなどからの輸入自動車及び部品に対し、最大25%の追加関税を課すことを検討しました。これも安全保障上の脅威を理由としていましたが、発動されれば世界経済に甚大な影響を与えると懸念されました。最終的に発動は見送られましたが、日米貿易交渉などにおいて、日本に対する強力な交渉圧力として用いられました。
トランプ関税の特徴
第1期に見られた「トランプ関税」には、以下のような際立った特徴がありました。第2期政権でも同様の傾向が見られていく可能性は非常に高いです。
強い保護主義・自国第一主義
「アメリカ・ファースト」を掲げ、米国の産業と雇用を守ることを最優先し、自由貿易体制よりも国益を重視する姿勢が鮮明でした。
二国間交渉の重視
TPP(環太平洋パートナーシップ協定)からの離脱に象徴されるように、WTO(世界貿易機関)などの多国間の枠組みよりも、二国間の交渉を通じて米国の要求を通そうとする傾向がありました。
予測困難性とトップダウン志向
大統領自身の意向が強く反映され、時にはツイッターなどで突発的に関税措置が発表・変更されるなど、その政策決定プロセスは予測が難しく、同盟国や市場を混乱させることがありました。
関税の「武器化」
関税を単なる貿易調整手段としてだけでなく、外交や安全保障問題における交渉カードとして戦略的に利用する姿勢が見られました。第二期政権でも関税を「経済的な武力行使手段」「経済的な抑止力」「経済的な防衛手段」として今後も使ってくる可能性は大いにあるでしょう。
これらの第一期トランプ政権の通商政策の特徴を理解しておくことは、今後のトランプ政権の通商政策を読み解く上で極めて重要となります。
トランプ関税で日本にはどんな影響が?
トランプ政権の関税政策は、同盟国である日本にも様々な影響を及ぼしてきました。そして、再び始動したトランプ政権(第2期)に対して、日本はどのような影響を懸念し、備える必要があるのでしょうか。
第1期政権下での日本への影響(振り返り)
まず、第1期(2017-2021年)における主な影響を振り返ります。
鉄鋼・アルミニウム関税の適用
日本も追加関税の対象となり、一部の鉄鋼・アルミ製品の対米輸出に影響が出ました。日本政府は適用除外を求めましたが、完全な除外は認められず、個別品目の除外申請などで対応する形となりました(その後、バイデン政権下で関税割当制度が導入)。
自動車関税発動の脅威
第一期トランプ政権では日本にとって最大の懸念材料でした。今回もこれは大きな争点となりそうです。もし最大25%の追加関税が発動されていれば、日本の基幹産業である自動車産業および関連の部品産業は壊滅的な打撃を受けていた可能性があります。この「脅し」が、後述する日米貿易交渉を日本側に促す大きな圧力となりました。
日米貿易協定の締結
自動車関税の回避などを主な目的として、日米間で新たな貿易協定の交渉が行われ、2019年10月に「日米貿易協定」および「日米デジタル貿易協定」が署名、2020年1月に発効しました。これにより、日本は牛肉や豚肉、農産品などで一定の市場開放を約束する一方、米国による自動車への追加関税発動は当面回避されることになりました(ただし、撤廃が明記されたわけではありません)。
為替相場への影響
トランプ関税や米中貿易戦争の激化は、世界経済への先行き不安を高め、リスク回避姿勢から比較的安全な資産とされる円が買われる(円高ドル安)圧力となる場面がありました。
企業への影響
米中貿易戦争の長期化は、中国に生産拠点を持つ日本企業にとって、サプライチェーンの見直しや生産拠点の移転・分散を検討させるきっかけとなりました。また、関税によるコスト増が企業収益を圧迫するケースも見られました。
第2期政権下での日本への影響(2025年4月現在の懸念と展望)
2025年1月にトランプ大統領が再任し、世界は再びその通商政策に注目しています。現時点(2025年4月)で具体的な政策はまだ明確になっていませんが、選挙期間中の発言などから、日本に対しても以下のような影響が懸念されています。
再び高まる包括的な関税リスク
トランプ大統領は、選挙戦を通じて、全ての輸入品に対して一律に10%の関税を課すという考え(「ベースライン関税」とも呼ばれる)を示唆しました。これが実現すれば、日本からの輸入品も例外なく対象となり、自動車、電子機器、機械類など、幅広い産業に深刻な影響が及ぶ可能性があります。さらに、特定の国に対してはより高い関税率(例えば中国に対して60%以上)を課す可能性も示唆しており、世界的な貿易秩序の混乱が懸念されます。
対中強硬姿勢の再燃と日本
中国に対する強硬な姿勢は第2期政権でも継続、あるいは強化される可能性が高いと見られています。米中対立が再び激化した場合、安全保障面で米国との同盟関係にある日本は、経済・外交の両面で難しい選択を迫られる可能性があります。サプライチェーンにおける中国依存の見直し(デカップリング、デリスキング)の動きがさらに加速するかもしれません。
自動車産業への圧力再燃の可能性
第1期と同様、日本の自動車および自動車部品が再び追加関税のターゲットとなるリスクは依然として燻っています。特に、米国の貿易赤字削減や国内雇用保護を重視する姿勢が強まれば、日本の対米輸出の柱である自動車産業への圧力が再燃する可能性は否定できません。
為替相場への影響
トランプ関税が実際に導入された場合の為替相場への影響は複雑です。世界経済の混乱やリスクオフムードから円高が進む可能性がある一方で、関税による米国内のインフレ圧力の高まりが米国の利上げ長期化観測やドル高(円安)を招く可能性も指摘されており、一方向ではない不安定な動きになることも考えられます。どちらのシナリオンも可能性がありすぎて市場参加者は混乱を強いられる動きとなる可能性は非常に高いです。
新たな日米貿易交渉の可能性
もし米国が一律関税などを導入した場合、日本は関税の適用除外や緩和を求めて、米国との間で新たな二国間貿易交渉を開始せざるを得なくなる可能性があります。その場合、日本側にも農産品市場のさらなる開放など、厳しい要求が突きつけられる事態も想定されます。
安全保障とのリンケージ
トランプ政権は、同盟国に対しても安全保障面での「応分の負担」を求める姿勢を鮮明にする可能性があります。日本が米国の安全保障戦略(特に対中国)にどの程度貢献するかが、関税問題を含む経済関係の行方にも影響を与える、いわゆる「リンケージ(連携)」の動きが強まるかもしれません。
日本企業や経済への具体的な影響シナリオ
仮に第2期トランプ政権下で再び広範な関税措置が発動された場合、日本企業や日本経済には以下のような具体的な影響が出ると考えられます。
輸出企業への直接的な打撃
関税が課されることで、日本製品の米国市場での価格競争力が低下し、輸出量の減少や現地での販売価格引き上げによる需要減退につながります。特に輸出依存度の高い自動車、一般機械、電気機器、精密機器などの業界への影響が懸念されます。
コスト上昇圧力
日本企業が米国から輸入している部品、素材、あるいは米国を経由する製品に関税がかかれば、生産コストの上昇につながります。また、世界的なサプライチェーンの混乱や輸送コストの上昇も、間接的にコストを押し上げる可能性があります。
企業の投資意欲減退
関税や貿易摩擦による先行き不透明感の高まりは、企業の設備投資や研究開発投資に対する意欲を削ぐ可能性があります。これは中長期的な日本の経済成長にとってマイナス要因となります。
国内物価への影響と個人消費の冷え込み
輸入製品の価格上昇は、日本の消費者物価を押し上げる要因となり得ます。物価上昇が賃金上昇を伴わない場合、家計の実質的な購買力が低下し、個人消費が冷え込むリスクがあります。
回避行動としての米国市場参入と工場移転
関税回避のためにアメリカ国内に工場を移設したり新設したり、その他企業活動をアメリカ国内で完結させようとする動きが日本企業にも波及しそうです。その結果国内の個人消費が冷え込み、国内企業の利益は海外に依存する結果となります。結果的に日本経済はゆるやかに国内資産の海外への流出がおきる可能性はあります。
もちろん、これらの影響の度合いは、発動される関税の具体的な内容(対象品目、税率、対象国など)や、日本政府および企業の対応によって大きく変わってきます。
トランプ関税発動でこれからどうなる? (2025年4月現在の展望)
2025年4月現在、第2期トランプ政権は発足から数か月が経過しましたが、具体的な関税政策の全貌はまだ明らかになっていません。今後の展開については不確実性が高いものの、いくつかのシナリオや市場への影響について考察します。(※以下はあくまで2025年4月時点での一般的な展望であり、実際の政策や市場の反応は異なる可能性があります。)
第2期トランプ政権の関税政策:実現可能性と具体的な形
公約の実現度
トランプ大統領が選挙期間中に掲げた「全輸入品への一律10%関税」や「対中60%超関税」といった公約が、どの程度、どのような形で実行に移されるかは依然として不透明です。これらの措置は米国内の物価上昇や産業界への影響、同盟国との関係悪化などを招く可能性があり、議会や産業界、さらには政権内部からの反発や現実的な制約によって、内容が修正されたり、段階的な導入になったりする可能性も考えられます。
対象の焦点
全ての輸入品を対象とするのか、あるいは第1期のように特定の国(特に中国)や特定の品目(自動車など)に焦点を当てるのかによって、影響の範囲は大きく異なります。
発動のタイミングとプロセス
関税措置を導入する場合、いつ、どのような法的根拠(通商拡大法232条、301条、あるいは新たな法律など)を用いて発動されるのかが注目されます。議会の承認が必要な場合と、大統領権限で比較的迅速に発動できる場合があります。
政権内の影響力
大統領自身の意向が強いことは確かですが、通商代表部(USTR)代表や商務長官、国務長官、財務長官といった主要閣僚や経済顧問団の意見が、実際の政策決定プロセスにどの程度影響を与えるかも重要なポイントです。
2025年4月現在は完全なトップダウンで政策を実行しています。
世界経済・貿易への影響シナリオ
もし大規模なトランプ関税が再び発動されれば、世界経済と貿易体制に深刻な影響を与える可能性があります。
世界的な貿易戦争の再燃リスク
米国による一方的な関税措置に対し、EUや中国などの主要国が報復関税で対抗すれば、世界規模での貿易戦争が再燃し、国際的な貿易ルール(WTO体制)がさらに形骸化する恐れがあります。
世界的なインフレ圧力の再燃
関税による輸入品価格の上昇は、米国内だけでなく、世界的なインフレ圧力を再び高める要因となり得ます。これは各国の金融政策にも影響を与えます。コストプッシュインフレとなるのでスタグフレーションも危惧されています。
世界経済の減速・景気後退リスク
貿易量の縮小、グローバルサプライチェーンのさらなる混乱、企業マインドや消費者マインドの悪化などを通じて、世界経済全体の成長を鈍化させ、スタグフレーション(不況下のインフレ)や景気後退(リセッション)に陥るリスクを高めます。
サプライチェーン再編、企業再編の加速
大企業が経営難に陥り、それによりM&AやTOBで企業再編が進むでしょう。さらには政学リスクや関税リスクの高まりを受け、企業は生産拠点の多元化(中国+1など)、同盟国・友好国間での連携強化、国内回帰といったサプライチェーン再編の動きをさらに加速させる可能性があります。
金融市場(株価、為替、金利)への影響シナリオ
トランプ関税の動向は、金融市場にも大きな変動をもたらす可能性があります。
株価
短期的には、関税導入への懸念や不確実性の高まりから、リスクオフムードが強まり、株価は下落圧力を受けると考えられます。中長期的には、関税によって打撃を受ける輸出関連セクターやグローバル企業と、国内産業保護の恩恵を受ける(かもしれない)一部のセクターで、株価パフォーマンスの二極化が進む可能性があります。ただし、世界経済全体への悪影響が顕在化すれば、市場全体が下落するリスクが高いでしょう。
為替
影響は非常に複雑で予測困難です。世界経済への不安からリスク回避通貨とされる円が買われる(円高)可能性がある一方で、米国内のインフレ懸念や金利上昇期待からドルが買われる(円安)可能性もあります。また、特定の二国間(例:米ドル/人民元)での変動が他の通貨ペアに波及することも考えられ、不安定な相場展開となる可能性があります。2025年4月現在は円高に進むとの見方が多数ですが、今後さらなる円安に向かってもなにも不思議ではありません。
金利
関税によるインフレ圧力の高まりは、FRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策運営を難しくします。パウエル議長解任(2025年4月18日現在)の話も出ており不透明感を増しております。利下げ開始時期が後ずれしたり、場合によっては再利上げが視野に入ったりする可能性もゼロではありません。市場のインフレ期待が高まれば、米国の長期金利にも上昇圧力がかかる可能性があります。
投資家としての心構え
このような不確実性の高い状況において、投資家はどのように備えるべきでしょうか。
- 情報収集の徹底: トランプ政権の具体的な政策発表、議会の審議状況、関係閣僚の発言、主要国の反応などを、信頼できる情報源から注意深くフォローし続けることが不可欠です。
- リスク分散の徹底: 特定の国、地域、業種、銘柄に過度に集中した投資はリスクを高めます。資産クラス(株式、債券、不動産、コモディティなど)や投資地域(日本、米国、欧州、新興国など)を分散させたグローバル分散投資ポートフォリオの重要性が増します。
- シナリオ分析とストレステスト: 「一律関税が発動された場合」「対中関税が大幅に引き上げられた場合」「現状維持の場合」など、複数のシナリオを想定し、それぞれのシナリオの下で自身のポートフォリオがどのような影響を受けるかを事前に検討しておくことが有効です。
- 長期的な視点の維持: 短期的な市場の変動やニュースに一喜一憂せず、自身の投資目標や時間軸に基づいた長期的な視点を持つことが重要です。狼狽売りなどは避け、冷静に行動しましょう。
- 専門家の意見も参考に: 信頼できるエコノミストや市場アナリストの見解、分析レポートなども参考にしつつ、最終的には自身の判断と責任において投資を行うという基本姿勢を忘れないようにしましょう。
まとめ
トランプ関税とは: ドナルド・トランプ米大統領の政権下で導入、または検討されている保護主義的(アメリカ・ファースト)な追加関税措置の総称です。第1期には鉄鋼・アルミ関税や対中関税などが発動されました。
日本への影響: 第1期の影響を踏まえ、第2期政権下(2025年4月現在)では、全輸入品への一律関税や、再び自動車などがターゲットとなるリスクが懸念されており、日本経済や企業への影響が注視されています。
今後の展望(不確実性): 関税政策の実現可能性や具体的な形は依然として不透明ですが、もし大規模な関税が発動されれば、世界的な貿易戦争の再燃、インフレ圧力、世界経済の減速、金融市場(株価含む)の混乱などを招くリスクがあります。
投資家の心構え: 不確実性の高い状況下では、情報収集、リスク分散、シナリオ分析、長期的視点を持ち、冷静に行動することが極めて重要です。
「トランプ関税」は、単なる貿易問題に留まらず、世界経済の構造や国際関係、そして私たちの投資活動にも大きな影響を及ぼす可能性のある重要テーマです。今後の動向を注意深く見守り、適切なリスク管理を心がけましょう。


