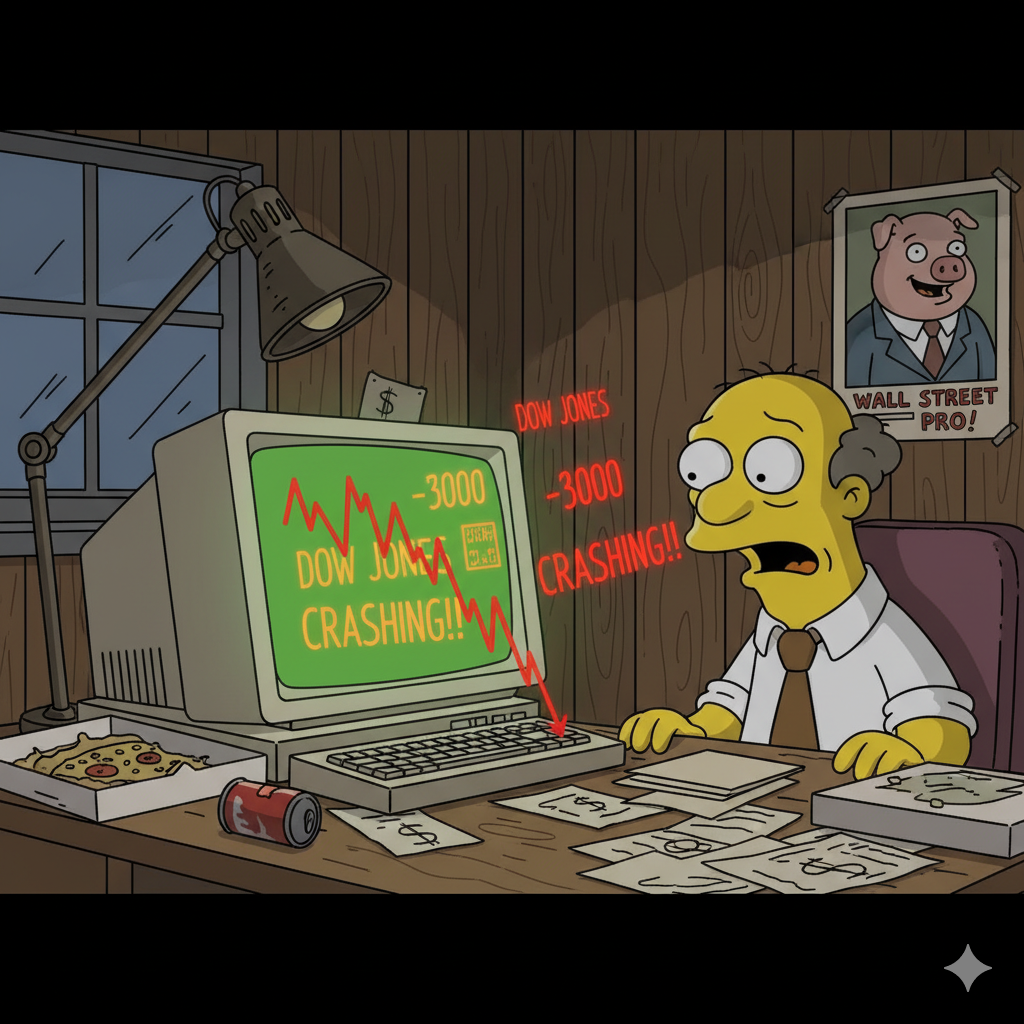リバランスとは?意味・必要性・やり方・頻度をわかりやすく解説【投資信託】
投資信託や株式などで資産運用を始めると、「リバランス」という言葉を耳にする機会があるかと思います。「リバランス」とは、一体何を意味するのでしょうか? なぜ投資において重要と言われるのか、具体的にどういうやり方でするのか、どのくらいの頻度で行うべきなのか、そして投資信託の場合も必要なのか、わかりやすく知りたいと思いませんか?
リバランスは、長期的な資産運用を成功させる上で非常に重要なメンテナンス作業です。
その意味や必要性を理解し、適切なやり方と頻度で実践することで、リスクをコントロールし、安定的なリターンを目指す助けとなります。
この記事では、「リバランス」とは何か、その基本的な意味から、必要性、具体的なやり方や頻度、投資信託における考え方、そして実践する上での注意点まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
リバランスとは?投資用語の徹底解説
リバランスの基本的な意味 ~資産配分の再調整~
リバランスとは、
投資ポートフォリオ(自分が保有している様々な資産の組み合わせ)において、最初に決めた資産配分比率(アセットアロケーション)が、市場の価格変動などによって時間とともに崩れてしまった場合に、その比率を元の計画通りに戻すために資産を売買し、調整することを指します。
「保有資産の再配分」や「ポートフォリオのメンテナンス」と言い換えることもできます。
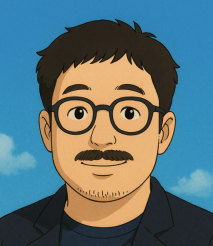
保有資産の組み換え=「売りたい資産を売って、売った資産で買いたい資産を買う」ことです。
例
あなたが投資を始める際に、「リスクを抑えつつ安定的に増やしたい」と考え、以下のような資産配分(アセットアロケーション)で100万円の運用を開始したとします。
- 国内株式ファンド: 50% (50万円)
- 国内債券ファンド: 50% (50万円)
1年後、株式市場が好調で国内株式ファンドの価値が20%上昇して60万円になった一方、国内債券ファンドの価値は変わらず50万円だったとします。すると、あなたのポートフォリオ全体は110万円になり、その内訳は以下のようになります。
- 国内株式ファンド: 60万円 (約54.5%)
- 国内債券ファンド: 50万円 (約45.5%)
当初目標とした「株式50%:債券50%」の比率から、株価上昇によって株式の比率が高く(54.5%に)なり、相対的に債券の比率が低く(45.5%に)なっています。
この崩れた資産配分比率を、元の目標である「株式50%:債券50%」に戻す作業がリバランスです。具体的には、値上がりした国内株式ファンドの一部(この例では約5万円分)を売却し、その資金で国内債券ファンドを買い増す、といった調整を行います。
なぜリバランスが必要なのか?その目的
では、なぜわざわざ手間やコスト(後述)をかけてまで、このリバランスを行う必要があるのでしょうか? その主な目的は以下の通りです。
- リスク管理: これがリバランスの最も重要な目的です。上記の例のように、値上がりした資産(多くの場合、株式など相対的にリスクが高いとされる資産)の比率が意図せず高まってしまうと、ポートフォリオ全体のリスク水準も当初想定していたよりも高くなってしまいます。そのまま運用を続けると、もし市場が急落した場合に、自分が許容できる範囲を超えた大きな損失を被ってしまう可能性があります。リバランスを行うことで、ポートフォリオのリスク水準を、自分が快適だと感じる適切なレベルに定期的に戻し、コントロールすることができるのです。
- リターンの維持・向上(長期視点): リバランスは、機械的に「値上がりした(相対的に割高になった)資産の一部を売り、値下がりした(相対的に割安になった)資産を買い増す」という行動を伴います。これは結果的に、「高値で売り、安値で買う」という投資の理想的な行動を、市場の雰囲気や感情に流されずに実践することにつながる可能性があります。特定の資産が一方的に上がり続けることは稀であり、長期的には各資産クラスが循環しながら上昇していくと考えれば、この機械的な売買が長期的なリターンを高める効果も期待されます。この効果は「リバランス・ボーナス」と呼ばれることもありますが、常にプラスの効果があるとは限りません。
- 当初の投資方針の維持と規律: 資産運用を始める際には、多くの人が自分の目標やリスク許容度に基づいて資産配分計画(アセットアロケーション)を立てます。しかし、日々の市場変動を見ていると、当初の方針を忘れてしまったり、感情的な判断で売買してしまったりしがちです。リバランスは、最初に決めた長期的な資産配分計画を守り、規律ある運用を継続するための重要なプロセスとなります。「計画通りに運用を続ける」という意志を再確認する機会にもなります。
これらの目的から、特に長期的な視点で資産運用を行う上で、リバランスは欠かせないメンテナンス作業と考えられています。
リバランスはしたほうがよい?投資信託別解説
リバランスの重要性は理解できても、「本当に必要なの?」「面倒くさそう…」と感じる方もいるかもしれません。また、投資信託で運用している場合はどう考えればよいのでしょうか。
リバランスは本当に必要? ~しない場合のリスク~
もしリバランスを行わずに長期間運用を続けると、どのようなリスクがあるのでしょうか?
- リスク許容度との乖離: 時間の経過とともに、値動きの大きい資産(特に株式)の比率が想定以上に高まってしまう可能性が高いです。これにより、ポートフォリオ全体のリスクが、自分が当初許容できると考えていたレベルを大きく超えてしまうことがあります。もしその後、市場が大きく下落するような局面が訪れた場合、想定以上の損失を被り、精神的にも耐えきれずに狼狽売りしてしまう…といった事態に陥りかねません。
- 資産配分の偏りと分散効果の低下: 当初はバランス良く分散していたはずのポートフォリオが、特定の資産クラス(例えば、好調だった米国株など)に大きく偏ってしまう可能性があります。これにより、せっかくの分散投資の効果が薄れ、特定の市場の変動にポートフォリオ全体が大きく左右されるようになってしまいます。
- リターンの機会損失: 機械的な「高値売り・安値買い」の機会を逃すことになります。もちろん、値上がりした資産がそのまま上がり続ける可能性もありますが、長期的に見れば、適切なリバランスはリスクを抑えつつリターンの安定化に寄与すると考えられています。
これらのリスクを考慮すると、やはり長期的な資産運用においては、原則としてリバランスは行った方が良いと言えるでしょう。面倒に感じるかもしれませんが、将来の安定した資産形成のための重要な一手間なのです。
投資信託におけるリバランスの考え方
では、投資信託で運用している場合はどうでしょうか? これは、保有している投資信託の種類によって考え方が異なります。
- 個別の投資信託を複数保有している場合
例えば、「日本株式ファンド」「先進国株式ファンド」「国内債券ファンド」などを、自分で決めた比率(例:40%:40%:20%)で組み合わせて保有している場合。
このケースでは、各ファンドの値動きによって時間とともに資産配分比率は崩れていきます。したがって、投資家自身が定期的に各ファンドの評価額を確認し、目標とする資産配分比率から乖離していれば、自分でリバランスを行う必要があります。具体的には、比率が高くなったファンドの一部を売却し、比率が低くなったファンドを買い増す、といった作業です。
- バランスファンドの場合
バランスファンドとは、1つのファンドの中に、あらかじめ決められた比率で株式や債券、REITなど複数の資産クラスが組み入れられている投資信託のことです(例:国内株式30%、先進国株式30%、国内債券20%、先進国債券20%など)。
バランスファンドの最大のメリットの一つが、ファンド内部で運用会社が自動的にリバランスを行ってくれる点です。市場変動によって資産配分比率が崩れても、ファンドマネージャーが定期的に、あるいは一定の乖離が生じた場合に、自動で元の比率に戻るように調整してくれます。
そのため、バランスファンドに投資している場合は、原則として投資家自身がリバランスを行う必要はありません。手間をかけずに資産配分を維持したい初心者の方や忙しい方にとっては、非常に便利な選択肢です。
ただし、そのファンドの目標とする資産配分が、本当に自分のリスク許容度や考え方に合っているかを最初にしっかり確認することが重要です。また、一般的にバランスファンドは個別のインデックスファンドを組み合わせるよりも信託報酬が高くなる傾向があります。
- ターゲットイヤーファンドの場合
バランスファンドの一種で、自分の退職予定年など、目標とする年次(ターゲットイヤー)を設定すると、その年に向けて自動的に資産配分を変更してくれるファンドです。一般的に、若い頃は株式などリスクの高い資産の比率を高め、目標年次が近づくにつれて債券などリスクの低い資産の比率を高めていきます。このタイプのファンドも、リバランスはファンド内部で自動的に行われます。
- 特定のインデックスファンドのみを積み立てている場合
例えば、「全世界株式インデックスファンド」や「S&P500インデックスファンド」のみを積み立てている場合。この場合、そのファンド内部では、連動対象の指数に合わせて銘柄の入れ替えや比率調整(リバランス)が行われています。
しかし、それはあくまで「株式」という一つの資産クラス内での調整です。もしあなたが、株式だけでなく債券や現金なども含めたポートフォリオ全体での資産配分(たとえば株式60%、債券30%、現金10%)を考えているのであれば、その比率を維持するためのリバランスは自分で行う必要があります。例えば、株価が大きく上昇して株式の比率が高まったら、積立額を調整したり、一部を売却して債券や現金の比率を高めたりする必要が出てきます。
このように、投資信託で運用している場合のリバランスの必要性は、保有しているファンドの種類によって異なることを理解しておきましょう。
S&P500やオルカンに個人で投資している方などはリスク分散の観点からも定期的に保有資産を点検し、リバランスが必要かどうか見極める必要があります。
リバランスの具体的なやり方
では、自分でリバランスを行う場合、具体的にはどのようなやり方があるのでしょうか? 主な方法を3つ紹介します。
- 方法1:値上がりした資産を売り、値下がりした資産を買う
- 最も基本的なリバランス方法です。目標比率よりも増えすぎた資産クラス(値上がりしたもの)の一部を売却し、その売却代金で目標比率よりも減ってしまった資産クラス(値下がりしたもの)を買い増します。
- メリット:目標比率に正確に戻しやすい。結果的に「利益確定」と「割安購入」を機械的に行える。
- デメリット:資産を売却する際に、税金(利益に対して約20%)や手数料がかかる場合がある。
- 方法2:新規の積立・追加投資資金を、比率が低下した資産に重点配分する:
- 毎月の積立投資やボーナスなどの追加投資資金を、目標比率よりも割合が低くなっている資産クラスに優先的に振り向けることで、全体のバランスを目標に近づける方法です。
- メリット:保有資産を売却しないため、税金や売却手数料がかからない。手間も比較的少ない。積立投資をしている場合に実行しやすい。
- デメリット:目標比率からの乖離が大きい場合や、追加投資額が少ない場合は、比率の修正に時間がかかることがある。完全なリバランスが難しい場合もある。
- 方法3:全資産を一旦売却し、目標比率で再購入する:
- 保有している全ての資産を一度現金化し、改めて目標とする資産配分比率に従って買い直す方法です。
- メリット:ポートフォリオを完全にリセットし、目標通りの配分を確実に実現できる。
- デメリット:売買の手間が最も大きく、税金や手数料のコストも最もかさむ可能性がある。頻繁に行う方法ではありません。
どの方法が良いかは、ポートフォリオの状況、追加投資の有無、コストなどを考慮して判断します。NISA口座(つみたてNISA、成長投資枠)を活用している場合、口座内での売却益は非課税なので、方法1も行いやすいですが、枠の再利用には注意が必要です。課税口座での売却には税金がかかる点を考慮しましょう。
リバランスする際の注意点
実際にリバランスを行う際には、いくつかの注意点があります。
リバランスの頻度はどのくらいが適切?
どのくらいの頻度でリバランスを行うべきか、悩む方も多いでしょう。これには唯一の正解はありません。頻繁すぎると売買コストがかさみ、リターンを押し下げる可能性があります。一方で、間隔が空きすぎると、その間に資産配分が大きく崩れ、リスク管理の効果が薄れてしまう可能性があります。
一般的に推奨される目安としては、以下の2つの基準があります。
- 期間基準(定時リバランス)
- 「年に1回」や「半年に1回」など、あらかじめ決めた期間ごとにポートフォリオの資産配分をチェックし、必要であればリバランスを行う方法です。
- メリット:シンプルで実行しやすい。忘れる心配も少ない。例えば、「毎年年末」「ボーナス支給月」「自分の誕生日」など、覚えやすいタイミングを決めておくと良いでしょう。
- デメリット:期間の間に市場が大きく変動した場合、一時的にリスク許容度を超えた配分になっている可能性がある。
- 乖離率基準(定率リバランス)
- 各資産クラスの配分比率が、当初定めた目標比率から一定以上(例えば、±5%、±10%など)乖離した場合に、その都度リバランスを行う方法です。
- メリット:資産配分のずれを常に一定範囲内に抑えることができるため、リスク管理の効果が高い。
- デメリット:常にポートフォリオの状況をチェックする必要があり、手間がかかる。市場の変動が激しい時期には、リバランスの頻度が高くなり、コストが増える可能性もある。
両者の組み合わせも有効です。例えば、「基本は年に1回リバランスするが、もしその間に±10%以上の乖離が発生したら臨時でリバランスを行う」といったルールです。
最も重要なのは、「自分にとって無理なく続けられるルール」を設定し、それを感情に左右されずに「機械的に実行していく」ことです。
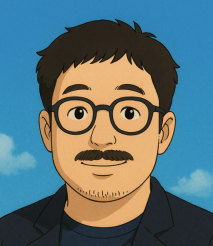
正解はありませんが、私は乖離率基準(定率リバランス)を採用しています
リバランスに伴うコストと税金
リバランスのために資産を売買すると、コストが発生する場合があります。
- 売買手数料: 株式やETF、一部の投資信託を売買する際に、証券会社に支払う手数料です。近年は無料の証券会社やプランも増えていますが、確認が必要です。
- 信託財産留保額: 一部の投資信託では、換金(売却)する際に、ペナルティのような形で基準価額から一定率が差し引かれる「信託財産留保額」が設定されている場合があります。目論見書で確認しましょう。
- 税金: これが最も注意すべきコストかもしれません。NISA口座などの非課税口座以外(特定口座や一般口座といった課税口座)で保有している資産を売却して利益が出た場合、その利益に対して約20%(所得税・復興特別所得税・住民税)の税金がかかります。この税負担があるために、リバランスを躊躇してしまう人もいますが、リスク管理という本来の目的を考えれば、必要なコストと割り切ることも重要です。
これらのコストを抑えるためには、前述した「方法2:新規の積立・追加投資資金を、比率が低下した資産に重点配分する」やり方が有効な場合があります。
資産配分比率(アセットアロケーション)自体の見直しも忘れずに
リバランスは、あくまで「当初決めた目標の資産配分比率に戻す」作業です。しかし、その大前提となる「目標の資産配分(アセットアロケーション)」自体が、現在の自分の状況や考え方に合っているかどうかを定期的に見直すことも、リバランスと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。
例えば、
- 年齢の変化: 退職が近づくにつれて、リスク許容度は一般的に低下します。若い頃は株式中心の積極的な配分でも良かったかもしれませんが、年齢を重ねたら債券や現金の比率を高めるなど、より安定的な配分に見直す必要が出てくるでしょう。
- 収入や資産状況の変化: 収入が増減したり、大きな資産を相続したりした場合、取れるリスクの大きさも変わってきます。
- 家族構成やライフプランの変化: 結婚、出産、子供の進学、住宅購入など、ライフイベントによって必要となる資金や許容できるリスクは変化します。
- 投資目標の変化: 当初は漠然と「資産を増やしたい」と考えていたのが、「10年後に住宅購入の頭金にしたい」「老後資金として〇〇歳までに〇〇円貯めたい」など、具体的な目標が定まれば、それに合わせた資産配分が必要になります。
リバランスを行うタイミング(例:年に1回など)で、同時にアセットアロケーション自体の見直しも行い、必要であれば目標比率を変更する、というプロセスを取り入れるのが理想的です。
感情に左右されないこと
リバランスを実践する上で、最大の敵は間違いなく自分自身の「感情」といえるでしょう。
- 値上がりして調子の良い資産を売るのは、「もっと上がるかもしれないのに売りたくない」という欲が出やすいです。
- 値下がりして評価額が減っている資産を買い増すのは、「さらに下がるかもしれないから怖い」という恐怖心が働きやすいです。
しかし、リバランスの本来の目的は、こうした感情的な判断を排し、あらかじめ決めたルールに従って機械的に実行することで、リスクをコントロールし、長期的なリターンを目指すことにあります。規律ある運用を継続するための重要なツールとして、冷静に、淡々と実行することを心がけましょう。
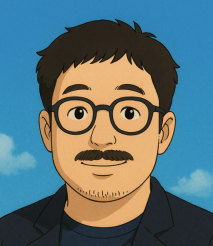
「ただルールどおりやってるだけ」と言い聞かせてやるのがおすすめです
まとめ
リバランスとは: 投資ポートフォリオの資産配分比率が崩れた際に、元の目標比率に戻すための調整作業です。その意味は「資産配分の再調整」や「ポートフォリオのメンテナンス」です。
必要性と目的: ポートフォリオのリスク水準を適切に管理し、長期的なリターンの安定化を目指し、当初の投資方針を守るために重要です。
投資信託での考え方: 個別投信なら自分でリバランスが必要ですが、バランスファンドやターゲットイヤーファンドの多くは内部で自動的に行われます。
やり方と頻度: 値上がり資産を売り値下がり資産を買う方法や、追加投資資金で調整する方法があります。適切な頻度に正解はなく、年1回などの期間基準や、乖離率基準など、継続可能な自分のルールを決めることが大切です。
注意点: 売買コストや税金がかかる場合があること、目標とする資産配分(アセットアロケーション)自体の定期的な見直しも重要であること、そして感情に左右されず機械的に実行することが求められます。
リバランスは、長期的な資産運用を成功に導くための、地道ですが非常に重要なプロセスです。車の定期点検のように、あなたの大切な資産を守り育てるためのメンテナンスとして捉え、規律を持って継続していくことをお勧めします。